建築は都市とどのような関わりを持てるのか――。
都市と建築の「空間の重なり」や「気配」に注目し、都市と建築の関係を考える。
東京大学大学院での講義「建築設計学第二」の書籍化。
「今、『都市からの撤退』と『都市の時代』をもう一度つなぎとめる方法が必要とされています。建築のお隣の都市計画の分野では、コンパクトシティやタクティカルアーバニズムなど、近年の動向を睨んだ取り組みが継続的に行われています。しかしながら、都市を構成するはずの建築の側からは、積極的な働きかけが行われてこなかったというのが私の問題意識です。この書籍では、『空間の重なり』という現象に着目し、21世紀なりの都市と建築の新しい関係を提唱します。」(「はじめに」より)
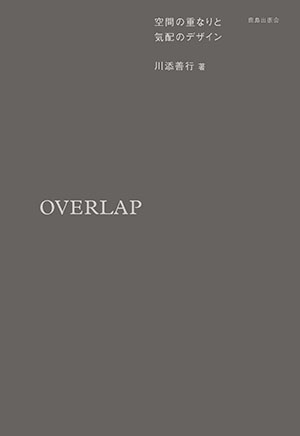
OVERLAP
空間の重なりと気配のデザイン
ISBN:9784306047105
体裁:四六・272頁
刊行:2024年1月
- 序章 はじめに
- 第1章 空間の重なり
- 第2章 フォルムとスペース
- 第3章 都市の時代
- 第4章 Architecture “for” the City
- 第5章 都市と建築を重ねる
- 第6章 気配のデザイン
- あとがき 学生たちとの対話と通して
- 参考文献
- 図版クレジット
他者性を織り込んだ寛容な建築
南後由和
○教育と研究の重なり合い
建築家の川添善行が東京大学大学院で担当する講義内容をベースとしてまとめられた『OVERLAP 空間の重なりと気配のデザイン』は、建築と文学、映画、音楽、脳科学などの多領域を横断する座学式の「教育」と、それらと連動した研究室での先端的な「研究」とが「重なり」合いながら編まれた書物である。随所に差し込まれた、著者自身の撮影による国内外の印象深い写真は、著者の建築へのまなざし―世界の建築の見方ではなく、建築を通した世界の見方―を読者が追体験できる仕掛けとなっている。講義の書籍化は、大学教員として理想のひとつであり、それを同世代の著者がやってのけていることに大きな刺激を受けた。
学生時代にオランダのデルフト工科大学留学を経て、東大の景観研究室に所属して土木の分野も越境することになった著者にとっての建築は、空間スケールと時間スケールの双方において射程が広くて長い。空間スケールは国土レベル、時間スケールは百年の計にまたがる土木という、より広範な視野から建築が捉え返されている。
○近代建築の問い直し
目次を見ると、例えば「フォルムとスペース」「都市の時代」「Architecture “for” the City」など、いわゆる大文字のキーワードが並ぶ。これら大文字のキーワードが並ぶ所以は、本書が近代建築と不可分な関係にある空間や機能主義などの概念を根底から問い直し、21世紀なりの建築が進むべき道標を指し示しているからだ。
この近代建築の問い直しの仕方が、本書の白眉のひとつである。近代建築の形の変遷を追うのではなく、そのような形が生まれた背後に、どのような思想や関連領域の影響が「重なり」合っていたのかが鮮やかに解き明かされていくのだ。例えば、自然科学の機械論的説明、進化論、唯物論という近代の価値観を特徴づける思想が、様式建築から離れた近代建築の土壌を用意したこと、絵画のキュビスムからの影響によって、フォルムではなくスペースという見方が獲得されたことなどのように。
○他者への寛容性
では21世紀なりの建築の道標とは何か。本書では「都市の建築」ではなく「都市のための建築」の記述に重点が置かれているが、ここでは二つのことに言及しておきたい。
一つは、著者の留学先であるオランダの国民性を示す言葉としてしばしば用いられる、他者への「寛容性」である。このことは「分ける空間」に対して、「重なる空間」を重視する著者の態度と通じている。「分ける空間」は、人種、階層、年齢、性別などのあいだに「分断」を生む発想と表裏一体である。著者は、このような分断、さらには排除を招きかねない建築の暴力性や政治性に警鐘を鳴らしたうえで、内部環境と外部環境、建築界内部と外部の価値基準、多義的な意味などを「重ねる」アプローチによって、バラバラになった世界をつなぎ合わせ、そのバランスを取ることに21世紀なりの建築の可能性を見出す。それは異質な他者やモノを無視および排除するのではない、寛容な建築のあり方である。
このことに関連して、著者が「建築的な部首」として漢字の「宀」(うかんむり)に着目し、うかんむり的な建築とは何かという問いを提起している点も興味深い。うかんむりは、例えば家や安のように、その下に入る漢字の意味を尊重しつつ、覆いをかける語義をもつという。完全に囲い込むのではなく、覆いによって対象をゆるやかに包摂しようとする、うかんむり的建築という発想は、かつてゴットフリート・ゼムパーが、ギリシア建築に先行する、人間社会の原初状態における「建築」の起源の四要素のひとつとして、屋根がもたらす作用を重視していたことを想起させる。
○気配や空気感のデザイン
21世紀なりの建築の道標のもう一つは、本書の最終章のタイトルでもある「気配のデザイン」である。これまで曖昧模糊なものとされてきた「気配」をデザインの主題として扱おうというのだ。五感のうちのいずれか単独の知覚ではなく、全体的かつ統合的な高次の知覚である気配のデザインについての著者の問題関心は、本書と対になるかたちで同時出版された翻訳本であるハリー・F.マルグレイヴ『EXPERIENCE 生命科学が変える建築のデザイン』で取り上げられている「空気感」というテーマと共鳴している。
アメリカの建築史家マルグレイヴは、建造環境に関する人間の体験を中心としたデザインについての思考方法を構築することの重要性を唱え、そのためには、建造環境と体験を「分ける」のではなく、建造環境への人間の関与によって引き起こされる「空気感」を、情動、知覚、社会、文化という複数の次元の「重なり」として捉える態度が求められるとした。特定の機能のための建築物のデザインではなく、「空気感」をまとった建築物のデザインに携わることがデザイナーの責務だとするマルグレイヴの主張は、「複数の主体や論理が共存し、多様な体験が得られる状態である」他者性を織り込んだ建築こそが、予測不可能性への期待値の高い、気配の醸成につながるとする著者の寛容な態度と重なり合っている。
(なんご・よしかず/社会学者・法政大学教授)
[初出:『SD2024』鹿島出版会, 2024]





