地図で都市文化を描く新手法。人気の街ポートランドを題材に、街のストーリーを美しいインフォグラフィックマップで描く。
地図で都市文化を描くあらたな試み。ポートランド州立大学の二人の地理学者が、地図を通じて「ポートランドらしさ」を表現することで、場所に対する理解を深め、地理的想像力をかき立てる、新しい地図学を提言する。「住みやすさ全米No.1」としてしばしばメディアで取り上げられ、風変わりでオシャレな街として旅行者を惹きつけ、環境や都市計画の分野で研究者の注目を集めるポートランド。その光と影、過去と現在、ユニークさ、「ポートランドらしさ」を創造力豊かな地図で表現する。100を超えるインフォグラフィックマップを掲載。旅行者はもちろん、地図の可能性を広げたい研究者、まちづくりに関心をもつ市民、インフォグラフィックに興味のあるデザイナーにぜひとも手に取ってもらいたい一冊。
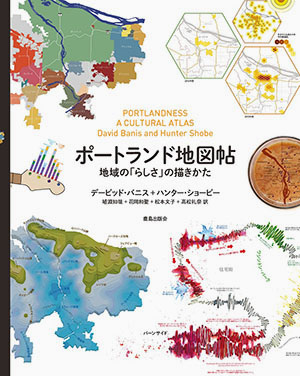
ポートランド地図帖
地域の「らしさ」の描きかた
ISBN:9784306046696
体裁:B5変・196頁(コデックス製本)
刊行:2018年11月
- オープニング・マップ
- 間取図でみるポートランド
- ネイバーフッド・カラーパレット
- PDXTube
- イントロダクション
- I.都市の景観
- II.過去と未来
- III.自然と野生
- IV.都市の見方
- V.ソーシャル・リレーション
- VI.フードとドリンク
- VII.ポップカルチャー
フィールドワークの結果をクリエイティブにまとめる方法を教えてくれる本
山崎 亮
ダイアグラムの魅力
ダイアグラムが好きだ。眺めるのも描くのも好きだ。90年代に建築を学んでいたからだろう。当時はオランダの建築家たちが中心になって、建築のプログラムを図化して示していた。空間の用途、人々の活動、そこでの経験など、目に見えないものやことを図化したダイアグラムに惹かれたものだ。その影響もあって、修士論文では人々の頭のなかにあるメンタルマップを扱った。同時に、シチュアシオニストが描く心理地図に興味を持った。いずれも目に見えないものを図化する楽しみがあった。趣味の活動として大阪府堺市でまちづくりに取り組んだ際も、江戸時代の堺の絵図から日用品が購入できる店の位置を割り出したり、地域に点在する動物の絵や置物などの写真を集めて地図をつくったりして、それらを『環濠生活』という手づくりの冊子にまとめた。
2005年にコミュニティデザインに取り組むstudio-Lという事務所を設立した。フィールドワークを実施、その結果を地図に落とし込み、ワークショップを繰り返し、市民の意見をダイアグラムとしてまとめていく。鳥取県智頭町(ちずちょう)の総合計画を策定したときは心が躍った。何しろ町の名前が「ちずちょう」である。当然、総合計画の別冊として「智頭町の地図帖」を制作して納品した。
ポートランド訪問
studio-Lのプロジェクトリーダーたちと毎年海外を視察する。我々と同じように市民参加型プロジェクトに取り組む人たちと会い、お互いの手法を話し合うためだ。これまでに、韓国、イギリス、アメリカ、イタリア、フランス、北欧などを訪れた。行き先はリーダーたちが話し合って決める。2016年はアメリカの西海岸を巡ることになった。目的地のひとつはポートランド。日本で紹介されるポートランドは概ねオシャレだが、実際には地域課題も存在するだろう。きっと、地域課題に取り組む団体の活動内容もオシャレなはずだ。そんな気持ちを携えてポートランドへ向かった。
イメージに違わずポートランドはオシャレだった。一方でホームレスも多かった。そして予想どおり、地域課題に取り組むクリエイティブな集団がいた。ホームレス支援のための仮設村「ディグニティビレッジ」、ホームレスが持つ技術を活かした「リビルディングセンター」、低所得者用住宅を供給する「セントラルシティ・コンサーン」、国際的な人道支援団体「マーシー・コー」。ポートランドはオシャレで輝かしい側面ばかりではないが、課題に対して創造的な取組みを続ける団体も存在する。とても勇気づけられた。
ヒントが詰まった本
ポートランドで滞在したホテルの近くに「パウエルズ書店」なる店があった。その入り口付近に『PORTLANDNESS』という本が平置きされていた。旅行案内っぽい本だ。どうせポートランドのオシャレな写真が並ぶような内容だろうと思いながらページを繰ると、予想に反して魅力的なダイアグラムで埋め尽くされていた。オシャレスポットを示した地図ばかりではない。標識に落書きされている場所、騒音が激しい場所、ホームレスの仮設住宅のある場所(ディグニティビレッジも示されていた!)など、魅力も課題も並列して示されている。即購入した。
2年後、この魅力的な書籍が邦訳された。それが本書『ポートランド地図帖』である。ポートランドについて知りたい人なら、本書を通じてかの地を深く理解することができるだろう。地域の歴史についても幅広く学ぶことができる。しかし、個人的にはポートランドに興味のない人にこそ読んで欲しい。特に、目に見えるものや見えないことをダイアグラムとしてまとめることに興味がある人に読んでもらいたい。フィールドワークやワークショップのまとめ方に関する多くのヒントが含まれているからだ。
本書に登場する地図の多くは、小学生や大学生がフィールドワークによって見つけ出してきたデータに基づいて作成されている。たとえば、大学生がまちを歩き、街路の雰囲気を「最高」「良い」「まあまあ」「悪い」「最低」の5段階で評価した結果を示した地図が掲載されている。極めて主観的な評価に基づく地図である。ある街路が万人にとって「最高」であるかどうかはわからない。でも、ある大学生にとって「最高」だと感じた街路が集まっているエリアが存在することは事実だ。途端に、どんなエリアなのか訪れてみたくなる。同時に「地図は客観的なデータに基づいて作成されるべきだ」という前提を払拭してくれる。
そのほかにも、ストリップクラブの位置を示した地図、お化けが出るといわれている場所の地図、鶏を襲うコヨーテが目撃された地点とそこからの距離を示す地図(小学生が2週間かけて調べた結果を地図化した)、匂いで地域を分けた地図など、独自の視点によるフィールドワークの結果をまとめた地図が並ぶ。いずれの地図も美しくて見やすい。
本書は、ひとつのまちをさまざまな視点で調査し、それらを美しくまとめる方法について教えてくれる書籍である。たまたま題材がポートランドだったというわけだ。見開きのページが水平になるまで開いても本が傷まない製本となっている点も含めて、学ぶべき点の多い地図帖であるといえよう。
(やまざき・りょう/コミュニティデザイナー、studio-L代表)
[初出:『SD2019』鹿島出版会, 2019]




