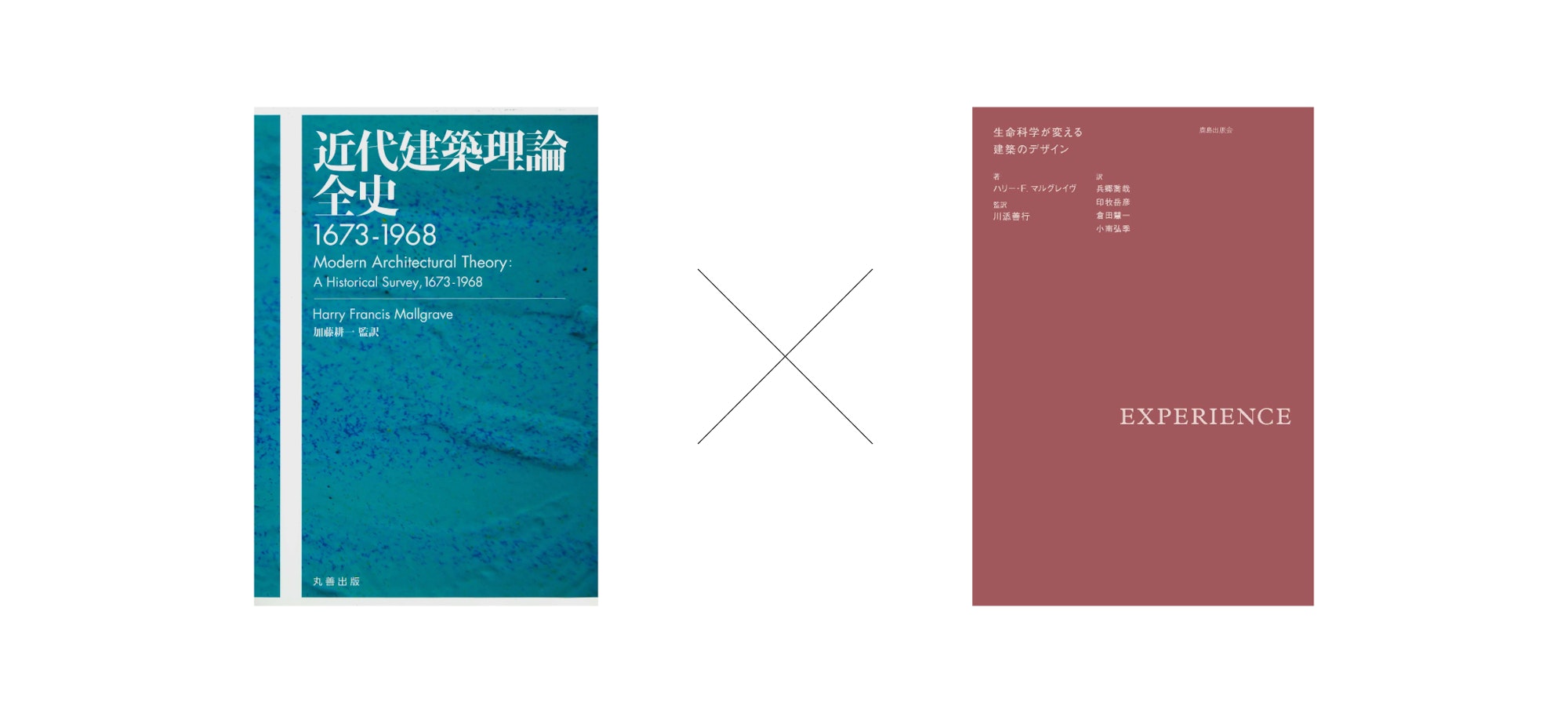
第1回 『近代建築理論全史1673-1968』×『EXPERIENCE』
加藤耕一(建築史家・東京大学教授)×川添善行
司会|印牧岳彦
2024年5月1日[於 東京大学工学部1号館3階講評室]
川添今日から始まる連続対談ですが、第一回のお相手は加藤耕一先生です。加藤先生がこの『近代建築理論全史1673-1968』という、およそ1000ページの非常に分厚い本を監訳されています。ちょうど『EXPERIENCE』という赤い本と、両方ともマルグレイヴが書いた本の翻訳ということもあり、そういう共通項の中で議論ができればと思っています。
印牧今日はどういうところから話を始めようかな?と思っていたのですが、『EXPERIENCE』のあとがきに、この本を川添先生にご紹介したのが加藤先生ということが書かれています。ただ、先ほど伺ったところ、記憶にないということなので(笑)、その辺りの経緯や川添先生が訳されるきっかけをまずお聞きできればと思います。それから、加藤先生はこれに先立って、鹿島出版会のサイトにも掲載されている『EXPERIECE』の書評の中で、本書とマルグレイヴのこれまでの仕事との関係というのを書いていただいておりまして、『近代建築理論全史1673-1968』などの仕事と『EXPERIENCE』の関係性というところを改めてお話しいただけたらと思います。
加藤最初にこの『近代建築理論全史1673-1968』を訳すきっかけになった話をしたいと思います。1000ページの辛い仕事でしたが、実はこれ、丸善の編集者の方がある日、僕の研究室を訪ねてきまして、『アーキテクツ・ブレイン』という、この『EXPERIENCE』の系譜に連なる脳神経科学系のマルグレイヴが最初に書いた本を持ってきて、これ訳しませんか?というお話だったんです。しかし僕はその頃、それよりもこの近代建築理論全史の本にすごく関心を持っていて読もうとしていましたので、 「いや、こっちですよ」と言いました。丸善に訴えるにあたって、これは「現代のギーディオンの『空間・時間・建築』であり、百年後の『空間・時間・建築』です」というふうに言ったところ、そういうことならば丸善から出さないわけにはいかないことになりました(『空間・時間・建築』の邦訳は丸善から刊行)。ただその頃から、マルグレイヴが脳神経科学から建築を考えようとしているということは、頭のどこかで気になっていました。川添先生にこの本を紹介したという事実はきちんと覚えていないのですが、川添研の博士課程の学生さんが行っている、脳波を測定しながら建築を見た時にどう反応するかという研究の副査をやらせてもらった時に、おそらくこの話をしたのかなという気がしています。
僕自身は、マルグレイヴが脳波や神経科学から建築をどう捉えようとしているのかということを、本の存在は知っていましたが、読んではいなかったんです。ただ、今紹介していただいたように、百年前の建築界において、空間というよくわからないものを心理学や感情移入という観点から捉えようとしていた理論家たちがいたからこそ、モダニズムにおける空間論が切り開かれたということを論じたマルグレイヴが、現代において脳波みたいなところから、建築をもう一度考えようとしているのだとすると、それは歴史的に見ても理論的に見ても建築の実践を考えても、 すごく面白そうだなと思っていたわけです。今回川添先生のチームがこれを訳してくださり、日本語で読めるようになったというのは、すごく重要なことだなと思って感謝しています。
川添オリジナルの『MODERN ARCHITECTURAL THEORY』が2005年で、赤い本の原著である『FROM OBJECT TO EXPERIENCE』が2018年なので、13年の時間があいているんですよね。2005年までこんな膨大な歴史的資料を考えていた人が、13年の間に今度は生命科学の文献を読みこんで、ある種新しい建築理論を組み立てようということですよね。13年の間にこんなことって、歴史家の人はできるものなのでしょうか?
加藤僕にはできないかもしれませんが、本当によく働く人ですよね。
川添すごいですよね。 さきほどお話にあった感情移入の話は、実は講義の中でよく話すのですが、なかなかうまく伝えられないんですよね。たとえば、「赤いものを見て、~と思う」というような、今の感覚だとなかなか説明が難しいなあといつも思っていて、今の建築理論にそういうものが反映しにくいために断絶があるとずっと思っていたのですが、この『EXPERIENCE』を訳してみると、その感情移入の話を生命科学の知見を使うと、実は直接的に引き出すことができるということがよくわかりました。実は彼がもともとやろうとしていたことと、現代の技術がようやく追いついた感じがします。
加藤そうですね。このマルグレイヴの『近代建築理論全史1673-1968』はすごく分厚い本で、全15章ぐらいある本なのですが、真ん中に9章というすごく薄い章があって、これが補説というおまけのような扱いで位置づけられているんですけれど、ここがおそらく一番重要なパートになっています。従来の近代建築史の中では、19世紀における歴史主義のような様式建築をつくっていたリバイバルのあり方と、それをモダニズムが否定して、全然違う建築が20世紀に生まれてくるという、そこの断絶がありましたということは指摘されてきましたが、ではそこがどうつながっていくのかというところが、きちんと説明されてこなかったんです。 ギーディオンは、そこを技術でつなごうとして、鉄の建築が19世紀に生まれてきた、さらに鉄筋コンクリートが20世紀に流れ込むというように技術の歴史とした近代を論じました。ペヴスナーは、ウィリアム・モリスのアーツアンドクラフツ運動がモダンデザインの始まりで、そこから20世紀に流れ込んでいくのだ、というように言うのですが、何故そこからモダニズムが生まれたのかというのは、この説明からでは全然わかりません。それをマルグレイヴはすごく気にしていて、それ以前の建築家たちが考えてきたことと、20世紀以降の建築家たちが考えてきたことを、当時のドイツにおける思想的なレベルでの建築理論の中の空間という哲学的な概念によって接続しようとしました。空間概念はドイツ語圏で19世紀から盛んに論じられるようになってきて、それまでモヤモヤと捉えきれなかったものが、当時のフロイトの精神分析なども関係しながら心理学や感情移入というようなかたちで、科学によって人間の心の動きを捉えようとすることで、空間というものを人間がどう捉えようとしたかということを考えた人たちがいた。そこからモダニズムの空間論が生まれてくるんだというストーリーを、この9章のところで考えているのだと思います。ただ、川添先生がおっしゃるように、感情移入論と言われると、「あ、感情移入したんだろうな」ということはわかるんですが、実際、そこで何が起こっているかよくわからなかった。その問題を、おそらく現代の神経科学のようなところから、もう一度捉え直そうとしていくということが、この研究の面白さなのだと思います。
川添補説というのは、加藤先生が書いたわけではないですね?これだけ薄いというのは、わざとこういう構成にしているんですか? 本として。
加藤わざとだと思いますね。ここが一番大事だぞと逆説的に示しているのだと思います。
川添しかも名前が「補説」というのも特徴的で、本としても非常におもしろいですね。
印牧書評の方でも書いていただいていましたが、その辺の19世紀の美学理論をまとめたアンソロジーをマルグレイヴが翻訳して出版しているんですよね。先ほど『近代建築理論全史1673-1968』は2005年に原書が出ているというお話がありましたが、マルグレイヴの仕事を少し補足しておくと、彼はもともとゴットフリート・ゼンパーの研究を出発点にしていて、80年代はじめに博士論文を出しています。それから80年代後半から2000年代はじめにかけて、アメリカのゲッティ・センターというところで、建築理論関係の翻訳をしていて、先ほどのアンソロジーもその中のひとつです。 さらにその後、鹿島出版会からもう1冊邦訳がある『現代建築理論序説』の原書が2011年に出ていて、同じ年に『The Architect’s Brain』の原書が出ています。そのような感じで、マルグレイヴ自身の仕事も展開していっているのかなという気がします。
加藤68年以降を扱った『現代建築理論序説』は、おそらくマルグレイヴと一緒にやっている若い人のメインの仕事なのだろうなっていう気がしますよね。
印牧ただ、あの本も最後が神経美学の話で締められていて、そこから将来の方向づけを与えようとしているのかなという印象を受けます。川添先生はこの『EXPERIENCE』という本や、マルグレイヴの仕事というのは、訳される以前はご存知でしたか?
川添不勉強ながら存じ上げなくて、加藤先生に「こういうのあるよ」と言われまして、私もその時、「へー」くらいの印象ですぐには動けませんでした。一方で、研究室として建築意匠を専門としていますから、やはり「美しさ」をどう客観的に議論しうるかという問題意識があり、そこで生命科学が使えないかというところからスタートしました。そうしている中で兵郷さんや小南さんもマルグレイヴの本の存在に気がついて、こういう文献がある、と。自分たちだけで実験をやっているといろいろなトライアンドエラーはできるのですが、やっていることの建築史的な位置づけが釈然としない時期が続いていたこともあり、せっかくなので訳してみることにしました。以前もケネス・フランプトンの本を読んでいたはずなんですけれども、マルグレイヴについての認識が薄いまま始めたような感じです。われわれの次のデザイン理論をどう考えるかという話と、近代をどう考えるかという話が、ちょうどマルグレイプで交差したイメージです。
印牧建築家の方の視点から、こういうのがどう見えるかというのが気になるところです。建築理論の役割についていえば、先ほど感情移入という概念がわかりにくいという話がありましたが、マルグレイヴが論じているように、抽象的な空間や形態に関する理論が結果的にモダニズムという新しい美学を生み出したということがあるんだとすると、このような新しい神経科学の理論や、今川添先生がやられているような研究が、例えば次のモダニズムや新しい建築の美学のあり方みたいなところに結びつく可能性もあるように思います。マルグレイヴの本はそうした理論の役割や意味のようなことを強調しているのかなと思ったんですけど、その辺はお考えとかありますか。
川添先週も講義の中で学生たちと議論したのですが、私が生産技術研究所という工学の全分野をカバーする組織にいることもあり、普段会う同僚たちは建築を専門にしない人がほとんどです。例えば光の研究をしているとか、ナノテクノロジーとか。彼らと話しているときに理論というと、言い方が難しいですが、それは「きちんとした理論」なんです。つまり、再現性があって、ある条件下においては、必ず同じことが繰り返されるものが理論で、繰り返されないとそれはただの現象であって、理論ではありません。つまり、建築の人がいう理論というのは、他分野の研究者たちがいう理論ではありません。建築の理論は考え方の道筋を意味していると思います。ですので、いつも建築の分野と建築ではない分野での議論に必ず齟齬が生まれているのが現状で、私はそれが気持ち悪くて、建築の言説は建築の中だけで閉じていていいのか、という問題意識がありました。そういうこともあって、生命科学の反応はきちんと定量化できることに着目しました。美しいものを見た時の反応というのは、ほぼ解明されていますし、それであれば分野外の人とも一緒に議論ができる。そういうものを求めていった先に生命科学になったんです。そうすると、建築における理論とは何なのだろう?というところに戻らざるをえません。ちょうどこの本のタイトルが理論ですけど、読んでみると、そういう意味での理論というのは出てこないですよね。いろいろな人のライフログのような、この人はこういうことを考えてここに行って、そこで誰々と会ってこういうことをやったというような、人生がずっと書かれているんですけれども、それを理論ということの面白さなのか、建築界特有の建築理論というものの不思議さなのか、お二人にお聞きしたくて、建築史家の人たちはこれを建築理論と言えてしまうのか?ある言説を取り上げた時に、それが建築理論なのか建築理論ではないのか、の境目は一体どこにあるのか?この本に載っている色々な人の物語は理論なのか、理論ではないのか?というのはどう見えているんでしょうか。
加藤日本の建築史の専門家は、あまり理論とは言わないんですよね。ですが、英語圏に行くと、ヒストリー&セオリーがセットで使われることが多い気がします。僕はあえて最近狙ってヒストリー&セオリーというふうに言っているんですけれども、その中で日本の建築家が理論と言っている時と、例えばアメリカでこのマルグレイヴのような歴史家がヒストリー&セオリーという時に違いがあると思います。海外の研究は、時代ごとにある種の必然として現れてくる理論を想定して、それを歴史の中で解明していくということなのではないかなと思うんですね。一方で、日本の建築家が理論に関心を持つ場合には、例えばル・コルビジエの理論もあれば、ヘルツォーク&ド・ムーロンの理論もあればというように、元々の理論の時代背景を意識せずに現代建築の理論として全部セットで論じうる。つまりそれは理論を歴史として見ておらず、歴史上登場したいろいろな議論の中から関心があるものを自分に引き寄せて、それを咀嚼し直して、自分自身の理論として提示したものとなっているわけです。それはある意味ではすごく面白いことなのですが、ヒストリー&セオリーとして考えると、それは元々の理論を歪めてしまっているようにも見えるところがあります。ある時代の中から出てきた理論を、現代文脈のなかで無理矢理使うというのは、もしかすると違うかもしれないと言うふうに思ったりします。
川添ヒストリー&セオリーであること。つまり「&」が大事ということですよね。私もこの本を読んでおもしろいと思ったのは、真ん中の9章のお話で、ここでは1920年代頃のモダンの建築家は断絶を主張していたけれども、実際そんなことは本当にあるのか、という点でした。始まりが1673年で、1673年からを近代として語っているという、その歴史的なパースペクティブがすごくて、クロード・ペローって近代なの?と。一般的に日本の建築教育では、近代はル・コルビュジエか、そのちょっと前ぐらいからですし、歴史様式なんて、それは近代ではないとおそらくみんなが思っていますよね。私はオランダで、カール・フリードリッヒ・シンケルとコンスタンチン・メーリニコフについてのリサーチをしていたのですが、オランダの建築家たちはそれが現代につながっているというイメージを持っていました。そういう意味では、シンケルが山登りしたとか旅行したとかというエピソードはとても重要なことなのかもしれません。もちろんシンケルはアルテス・ムゼウムを設計します。生まれてくる空間性は、その都市への振る舞いや大きな列柱など、すごく近代的な空間だなぁと思う一方で、昔私が学生の頃に教わったのは、あれは新古典であって近代の前ですと言われていました。その意味では、1673年から近代と捉える人たちと、20世紀から近代が始まったと思う人たちでは、全然建築への深みが違います。シンケルが今と繋がっていると思える人たちは、やはりヒストリー&セオリーをきちんと理解できますし、たかだか百年の中でしか近代を考えられないと、面白いダイアグラムが理論だと勘違いしてしまう。そうした、そもそもの土壌の違いをこの1000ページを踏まえて感じてしまったというのは、一番衝撃的な出来事でしたね。
印牧近代をかなり広いタイムスパン、連続的な歴史スパンで捉えるという点で言うと、加藤先生がやられているリノベーションのお仕事がありますけれども、あれも近代を500年ぐらいのスパンで見ようとしているという意味では近いのかなという気もしますが、加藤先生から見て、マルグレイヴの歴史観というのは、賛同するところが多いのでしょうか。
加藤この1673年が近代の始まりというふうにこの本を描いたマルグレイヴのテクニカルなやり方はかっこいいなと思います。 ただ、僕もじゃあそこが始まりだというかどうかは、そういう意味では賛同はしてないのかもしれません。マルグレイヴが1673年を出してきた背景にあるのが、鉄筋で補強した石積みの建築を用いた、クロード・ペローです。それはギーディオンがモダニズムのルーツとして鉄を考えた時に、1779年のコールブルックデールの鉄橋までしか遡れなかったのに対して、いや、鉄の問題を考えるならばここまで遡りうるのだということを示したわけです。さらにいえば、マルグレイヴはゼンパーの言うテクトニックの好例として鉄筋の補強を捉えているような気がします。ギーディオンの近代建築史は産業革命以降の鉄の建築まで遡ったけれども、産業革命よりもっと前に鉄を使った鉄筋組積造の建築があったわけで、もしかするとそれは、現代の鉄筋コンクリートまでつながるような、そういうアイデアだったのだということを示したという意味では、かっこいい歴史だなと思います。
川添では加藤先生が近代を書くとしたら、始まりはどこになるんでしょうか?
加藤書く時に考えます、すみません。笑
川添結局それって、歴史に対する見方ですよね。
加藤その時、何を論じたいかだと思います。
川添近代の終わりに関する記述も気になったのですが、1968年、チェコの国の制度が変わるというような話や、アメリカの公民権運動が盛んになって、キング牧師が殺された年でもあり、パリの5月革命など、割と社会的な不安定さの中で、時代の変わり目であるぐらいしか書かれていないような気がしたんですけれども、この68年というのは近代の終わりなのでしょうか?
加藤これはもしかすると、日本の我々には一番理解できないところなのかもしれないですよね。日本だとせいぜい安田講堂の学生運動みたいなところでしか捉え切れてないですよね。実際、パリの5月革命も同じような現象が起こっているんだけれど、もっと大きな社会の断絶があり、建築理論も建築教育も大きく変化したのだと思うのですが、日本の私たちはそこを感覚的に理解しきれていないので、わかりやすい区切りとして1968年で切ったのかな、ぐらいにしか理解できていないですね。
川添ちょうど加藤先生は1973年生まれですね。自分の300年前の本からちょうど自分の5年前までという、歴史的なパースペクティブを意識されているのではないかと思いました。近代以降はご自身で理論を作る、ということを踏まえた1000ページなのかなと思いました。
加藤頑張ります。
川添『OVERLAP』の中でも書いたとおり、アルド・ロッシの『都市の建築』が1966年ですね。ちょうどモダンへの問い直しというのが起こり始めた年あたりですよね。コンテクスチュアリズムも出てきますし、ただその近代の乗り越えがテーマにあって、単一的な機能からもう少し機能を複合させたほうがよいのではないか、というようないくつかメッセージがあると思います。近代は終わったのか、それともまだ近代の中にいるのか、みんなが気になっていることですよね。槇さんが『漂うモダニズム』の中で、価値観がすでに共有されない時代になってきたとも話していますが、学生たちが感じているのはおそらくそういったことで、それは全員が同じ方向を向く時代よりもいいことのような気もしますし、ただ、力強さがだんだんなくなってきているような気もしています。そのあたりは、『近代建築理論全史1673-1968』と『EXPERIENCE』の間ぐらい、まさに現在の話なのかもしれないですが、そういうものの問い直しというのは建築史家はやるものなのでしょうか?
加藤すごく関心はあります。先ほど川添先生が指摘したように、日本では近代建築と言ったらル・コルビュジエ以降というような捉え方が一般的です。しかし、その100年でしか近代建築、近現代の歴史というものを捉えなかったとすると、その100年は人口増加の時代であり、経済成長の時代であり、20世紀という、歴史上で見ると異常ともいえるような特別な時代の建築理論であったと思うんです。それが今、少なくとも日本では人口減少が始まり社会が大きく変動する時代であるとすれば、どちらかというと、この100年ではないところを見なければ、参考になる理論は見つからないのではないかという気がしています。その意味で、近代を乗り越えることは必要だと思っていて、乗り越える一つのやり方として、近代が示すタイムスパンを100年よりも広げていくというのはありだろうなという気がしますね。
印牧『EXPERIENCE』に関して言うと、68年あたりの記述について1つ思うのは、ポストモダンの建築理論に対して、非常に批判的ですよね。先ほど自然科学の分野と理論の捉え方が全然違うというお話がありましたけど、人文系と自然科学系の断絶のようなものが、その頃に始まったという、そしてそれをもう一回統合しなければいけないという話になっているんですけど、20世紀後半の建築界の動向に対して、マルグレイヴの当たりが非常に強いというのを感じます。それはマルグレイヴが仕事を始めた時期がちょうどポストモダンの時代だったということも関連しているのかなという気がするんですが、そのあたりの評価というのはどう思いますか?
加藤ポストモダン批判に関しては、建築を視覚で捉えるということと、言葉で捉えるということ、これがおそらく20世紀が一番やろうとしたことであり、マルグレイヴはそこを強く批判していました。それに対して、言葉でもビジュアル的な図面でも表現できない何かを捉えるのが感情移入、今の脳神経生命科学ということなのだと思います。ポストモダニズムは典型的に視覚の芸術であり、言葉の芸術であったので、それがポストモダニズム批判の背景にあると理解していました。
印牧もう一点、マルグレイヴの見方で気になるところがありまして、68年あたりの話で、マルグレイヴはカウンターカルチャー的な動きに対しても批判的に見えます。『近代建築理論全史1673-1968』の方でいうとアーツ・アンド・クラフツの運動に対しても評価は厳しいですし、建築を社会改革の道具として捉えるというようなところをあまり認めていないのかなという気がしました。川添先生の『OVERLAP』では、課題解決型のデザインに対して、建築は必ずしも課題解決を目的とするものではないということが書かれていたのですが、その辺はどうお考えでしょうか。
川添それって、社会の前提ではあると思うんですよ。誰も環境を壊したいとは思っていませんし、役に立ちたいと思っているとは思いますが、それを目的としたからといって建築はつくれないだろうなという気がしています。環境に良い建築はつくれます。ただ、環境に良いというところが建築を決定できるわけではなくて、結局誰かが決めているんですが、その決めていることをただ隠しているだけのように使われているのが難しくて。 建築って、もっと他にやるべきことが本当はたくさんあって、例えば人が集まる時にどういう場所だったらいいのかとか、その人が最後、その家で死ぬとしたら、どういう家であってほしいのかとか、本当は建築にしか考えられない問題がたくさんあるんですけれども、それに向き合わないための言い訳として、社会的正義が繰り出される構造に私は常に違和感を持っているっていうような感じです。
加藤社会的正義という意味では、モラリティの問題というのが、 20世紀の建築をシャープにしたけれども、つまらなくもしたという気がしています。建築をモラルで捉えるというのは、モダニズムのすごくストイックな姿勢の一つだったと思うんですよね。そのことが装飾批判もやったかもしれないし、モダニズムを形作っていって、それはそれで一つの時代を作った。けれども今なお、例えばエコロジーのような問題をモラルの観点から捉えてしまうと、これはやっちゃいけませんというふうになるので、それは建築の幅を狭めるばかりだと思います。けれども、モラルとしてではなくて、面白いからエコロジーの問題を考えるというようなことができると、もう少し建築の幅が広がると思うし、今川添先生がおっしゃっていたようなことができそうな気がします。
印牧建築史の分野だと、デイヴィッド・ワトキンの『モラリティと建築』という有名な本がありますが、モラリティを強調しすぎることで失われる部分があるのだとすると、建築理論はそうした社会正義の正当化とは違うところに可能性があるんじゃないか、というお話なのかなと思いました。
会場質問建築理論がこれからどう変わっていくか、これからの役割についてどう考えたらよいでしょうか。
印牧先ほど、この本が21世紀のギーディオンだというお話がありましたが、マルグレイヴがやろうとしていることは実際ギーディオンに似ていて似ている部分もあって、これまでの歴史を使いつつ、これからの建築の方向づけを与えようとしていると思うのですが、そのような役割をこれから建築史や建築理論は果たしていくべきなのでしょうか。
川添いくべきでしょう。建築史の人は歴史ばっかり見てどうするのというのは、思っています。
印牧20世紀後半にギーディオン的なやり方に対する批判がすごくあったと思うんですよね。ギーディオンだけではなく、ぺヴスナーなんかもそうですけど、近代建築を正当化するために歴史が使われてきたという経緯があって、それ以降、歴史家はそういう方向づけを与えないようにしてきたのではないかと思います。ただ、それからまた50年くらい経って、改めて新しい大きな物語を作る必要性が感じられているのかなという、マルグレイヴもそういう流れにあるのかなという気がします。
加藤ギーディオンが歴史を作った時代は、大きく社会が変動した時代だったと思うんです。19世紀的な建築の作り方がもはや成り立たないとなった時に、歴史を語りつつ、未来の理論を示すみたいなことをやったんだと思います。その意味では、20世紀の一直線に成長してきた社会にとっては、20世紀後半のポストモダニズムまでの時代の中では、新しい理論を捻り出す必要はおそらくなくて、歴史を丁寧に間違いなく研究するということが歴史家の役割だったのだと思います。しかし今、これだけ社会が揺れ動いていて、建築もどこを目指せばいいかわからないという時代になった時には、やはり僕らも歴史を見ながら未来を見通すみたいなことをやらなければいけないなとは思います。難しいですし、あまり危ないことをすると仲間から批判されるんですけれども。
川添歴史家の役割には大きく期待しています。工学の中で歴史が重要に位置づけられているは、最近土木でも増えていますがかつては建築だけですよね。理由はシンプルで、例えば車だったら、それは最新型の方が性能はいいわけです。電子部品もそうですけれども、マッキントッシュも新しいのであればみんなそちらが欲しいですよね。けれども建築は、常に新しいものが必ずしもいいわけではない。私たちが今どこにいて、どこに向かおうとしているのかという大きな歴史観がなければ、建築はつくれません。技術的な試行錯誤はできますが、設計はできないわけです。
われわれは分野的には「歴史意匠系」ですから、建築家の活動に建築史家が入ってきてもらって、本当はそこがもっと接続しなければいけない。しかし残念なことに、これまではあまりうまく連携ができているとは思えないんです。今おっしゃったとおり、マルグレイヴのやり方というのは、われわれ設計する人が見ても非常に勉強になりますし、『EXPERIENCE』ではそれが直接的に書かれています。『近代建築理論全史1673-1968』もそうですね。歴史と設計というのは、合わせ鏡というか、そこの役割をもう少し深くしていきたいなと今日お話を伺っていて思いました。
加藤その意味でも、このような企画をつくっていただいた川添先生に感謝です。
川添これを始まりにしたいですね。例えば、自分はフランスの何世紀を専門にしていますとか、自分は寺院の研究をしていますとか、研究者としてはどうしても範囲を限定せざるをえません。一方で、大局観や歴史観をリアルタイムでやり取りする状況がおそらく今後の建築界にとってとても重要になってくると思います。自分たちがどこに行ったら良いかわからないということに関しても、それは個々人で判断することだとは思う一方で、クロード・ペローから近代を語れる人たちに、われわれ自身も近づいていかなければ考えようがないのかなという気がします。
印牧歴史と設計の新しいコラボレーションの方向性が見えてきましたね。
会場質問今の現代の建築がどんどん発散し一つのナラティブで語れないというお話があったと思いますが、それは今同世代で生きているから、そう発散しているように見えるだけで、100年後などから見た時には、これも一つのナラティブとして語れるのでしょうか。それとも19世紀やそれぐらいまでにおこっていた大きなうねりのようなものは、現在にはないというように感じていらっしゃるのか。歴史をずっとやられている方から見て、今の現代の建築をどう考えていますか?
加藤正直言うと、それが見えない時代だと思います。下手したら、100年後から見た時には、この時代には面白いものは特に何もありませんでしたねと、すっ飛ばされてしまう時代になってしまうかもしれないという危機感があります。いろいろな方向のいろいろな理論というのは、それぞれの見地からみんなもがいていて、いろいろなことを勉強して、いろいろな方向性を出しているんですけれども、やはり今の時代だからこそ出てくる大きな理論みたいなものがおそらく共有できていないし、見えていないんですよね。見えていないからこそ、そういう状況になってしまっている気がして、その中でやはりこっちの方向ではないかというものを見つけることが重要だと思います。その大きな流れの中で、個性を出していく方向というのは、あるべきだと思うんですけれども、それ自体が見えないというのが今の危機の状況かなという気がしますね。
川添理論がないと歴史にならないんでしょうか? 例えば、すごくかっこいい建築が一個できました、ただそれはポツンとできて、前にも後にも残っていません、なんでそれができたのかもよくわからないっていうような場合、それは建築史ではないんでしょうか?
加藤いや、それも建築史だと思います。ただ、語るのが難しいんです。ページの中に、こんなのありましたと写真は載せたいですし、クレジットは載せたいんですけれども、ただそういう建築を語るのはすごく難しいです。歴史の中でもたまにそういう建築があると思います。
川添『近代建築理論全史1673-1968』には、建物の写真がほとんど出てきませんし建築もあまり出てきません。「誰がどこに行って何をしました」というような事がずっと300年間書いてありますが、これは建築史の本なのでしょうか?それとも人物伝なのでしょうか?
加藤それが理論史ということなんじゃないでしょうか。各章の冒頭1パラグラフか2パラグラフぐらいで、この時期の社会状況みたいなことを簡単にダイジェストされていて、その中で建築家たちがどこ行って誰に会ったというような話が始まるので、やはりその時代のその社会状況の中で、建築が何を考えてどう動いたという、そういうことなのだと思います。
川添常にある時間軸の中での位置づけを考えて語れるからこそ、それが理論であるという。確かにそうかもしれませんね。
印牧でも、理論史の書き方がこれだけかというと、別の書き方もありそうな気はしますね。
加藤では数年後を目標に頑張ろうと思います。
川添新しい建築理論のゆくえ、とても楽しみです。

(建築史家・東京大学教授)


